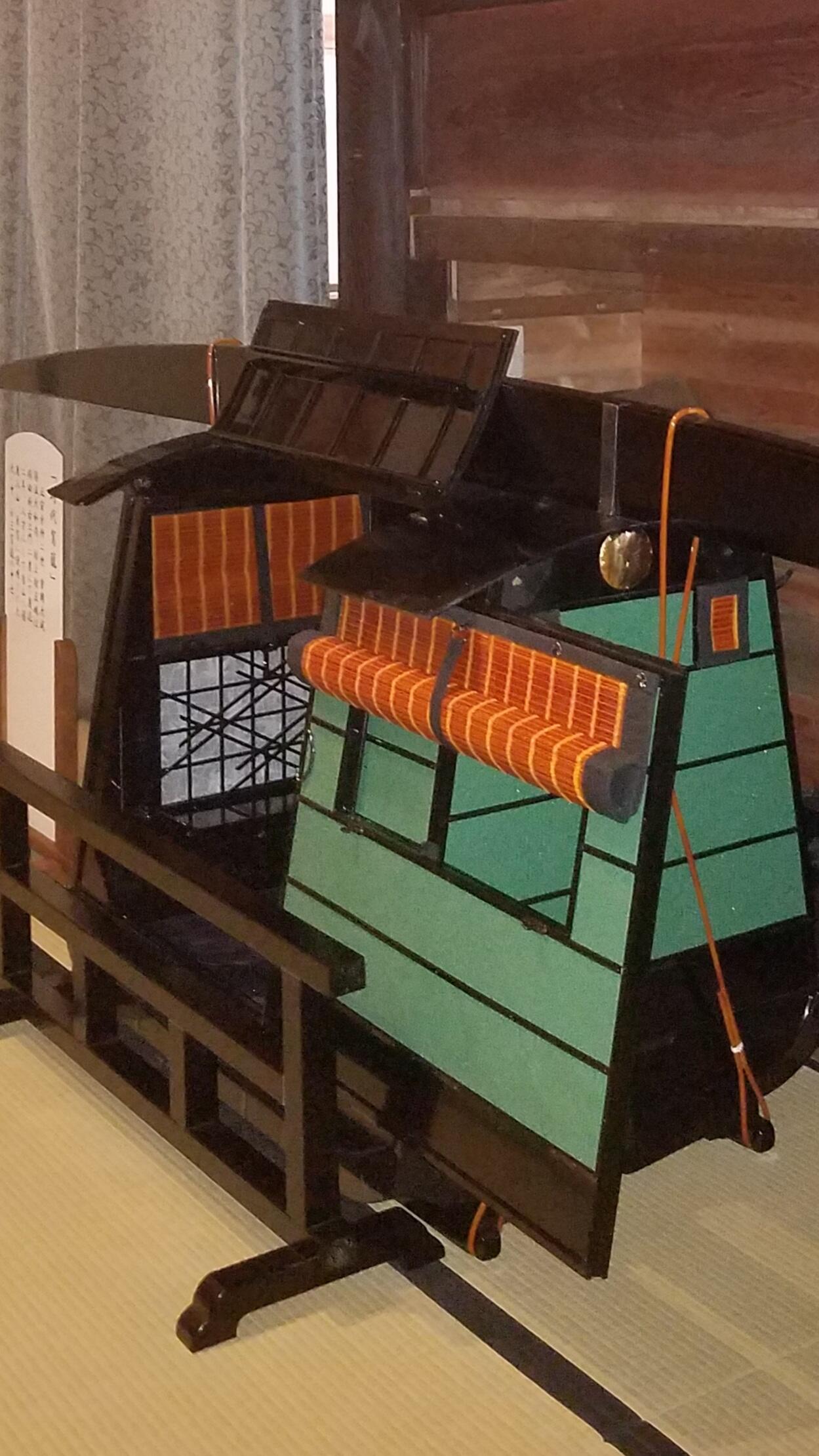第二段
本文
萬法ともにわれにあらざる時節、まどひなく、さとりなく、諸仏なく、衆生なく、生なく、滅なし。
語注
・万法...「まんぼう」か。前段の「諸法」と同じ意味で使われていると思われる。あらゆる物事。
・われ...ここはかなり重要なところではないかと感ずる。仏教中でも多くの意味があると思われるこの語だが、どう解したらよいのであろうか。現状は判断要素が足りないが、素直に解釈すればやはり「我」であろう。
現代語訳〈緑本〉
万法(と言われるあらゆるものごと)すべてそれ自身一定したものではない、その時節(とき)、迷いもなく、さとりもなく、諸仏もなく衆生もなく、生もなく滅もない。
自主的解釈
「あらゆる存在や事象のそれぞれが皆、『我』を持たず、また常住不変の存在は「ない」という見方にたつならば、惑いも悟りも諸仏も衆生も生も死も、確固たる存在のものは何一つないことになるであろう。
この段は個人的には前段より解しやすいと感じる。「諸法無我」の道理を言ったものとも推察出来得る。
ただし自主訳にも記した通り、「確固としてあるものはない」のは理解できるが、それがなぜ「ない」と断言されるのかが分かりづらい。
個人的にはそれでも「ある」側面が残されているように感じてしまうのだが。それさえ見込まれての御文であろうか。
第三段
本文
仏道もとより豊倹より跳出せるゆゑに、生滅あり、迷悟あり、生佛あり。しかもかくのごとくなりといへども、華は愛惜にちり、艸は棄嫌におふるのみなり。
語注
・仏道...前二段を鑑みるならば、この語も「あらゆる物事」、「世界そのもの」と訳せそうなものであるが。「仏法」と同意ゆえそれでよいか。
・豊倹...豊は多、倹は少、ひいては相対立する二つのことをいう。二項対立の概念。
・生仏...「衆生と仏」か。
・愛惜...愛し惜しむこころ。
・棄嫌...棄て嫌うこころ。
現代語訳〈緑本〉
仏で生きる生き方は、本来豊(あり)倹(なし)という相対の世界から跳び出ているのであるから、(その上で、)生と滅もあり、迷と悟もあり、衆生と仏もある。それはそういうことなのであるが、花が咲けば愛惜の心が起こるが、愛惜のまま花は散るのであり、草が生えれば棄て嫌う心が起こるが、嫌われながら草は生えるばかりである。
本文の出典元
・豊倹:*ユタカナルトマズシキト(『清本』左注)。
*茶器幷びに其の余の衣物の如き、並びに家の豊倹に随ふ。(『禅苑清規』一、辦道具)
*家門豊倹、時に臨んで用ゐ、田地優游歩に信(まか)せて移る。(『宏智広録』二)
*亦た只だ家の豊倹に随う。(『圜悟録』十五)
・生仏:光明一点、乃ち生仏之枢機。(『宏智広録』一)
・花は愛惜に...
:*問ふ、「如何ならんか是れ和尚の家風」。師(牛頭精)云く、「華従二愛惜一落、草遂二棄嫌一生」。(『広燈録』二十五、牛頭
精章)
*上堂云、人々具足、箇々円成。甚麼(なに)と為(し)てか法堂上草深きこと一丈なる。這箇の消息を会せんと要す麼(や)。良久して云く、花依二愛惜一落、草遂二棄嫌一生。(『広録』一)
自主的解釈
「仏の境涯から述べる世界は、もとより豊倹や常断の両辺を跳出しているからこそ生滅があり、迷悟があり、生仏があり、なればこそ愛惜で華は散ってしまい、棄嫌で草は生えてしまうこともあるのだ。
『啓迪』によれば、「このなりといへどもは、いつもの筆法で、なればということだ」と示している。
よって解釈も上記の如くに訳してみたが、やはりどうもしっくりとは来ない。
ここは自身でも解釈の折り合いの付けにくい所である。
有りや無しではない、としながらなぜみな「あり」になるのだろうか。「有りもあるし、無しもある」故に「ある」ということであろうか。
最後の華と草の文は「我々の主観によって物事は有りだったり、無しだったりする。」ということであろうとは思うのだが、いかんせん本文の通りが得心し難い。
ここで西有禅師の特異ともいえる行学の経歴に思い至った。
幕末と言うには、まだ早すぎる感もある文政四年に生誕し、明治四十三年まで活躍された禅師は、自ら『啓迪』の中で述懐されるが如く、明治への転換期、今では歴史上の出来事と思われる「彰義隊」と相まみえ、命のやりとりともいうべき問答をしている。
また、その生没年代から江戸時代を半生、明治時代を半生とする、激変した時代文化を同じく体験され、その中で宗乗以外の学問への探究心も強く、三論や唯識は勿論のこと、華厳や天台に至るまで幅広い見識を提唱されたと言われている。
これは、天台から曹洞に転じたとされる小田原海蔵寺、月潭全竜のもとで長く修行し「瑾英」と改名していることにも関係があろう。
そこで近年、道元禅師もその学徳に思慕され、禅師の学識や著書にも多くの影響が見られるとする、中国天台教学の初祖、天台智者大師智顗の名著、『摩訶止観』等にも記される五時八教の教判は化儀また化法の四教、即空即仮即中の三観、六即等の教相も用いた解釈も適宜、その土台として取り入れたい。
特に『摩訶止観』については、長い仏教史の中にあっても、禅(止観)に対して真正面から教相で臨んだ唯一希有な大作と呼べるもので、天台大師をして智者大師たらしめている中心的著述ともいえる。
さて『啓迪』では各段の一々が皆「現成公案」として、浅深のないことを強調されている。その上で誤謬しそうな例を取り上げながら、各三段の初後、浅深、大小の見方を戒めている。
まさに禅における頓悟の優位性を保ちながら、決して順次次第も疎かにしない、天台智者大師の化法の四教の円教より四教を観じ、また空・化・中を即義で結ぶ手法とも似ている。
ただし。この三段に関しては空・仮・中の三観では割りにくい。
そもそも「現成公案」の三段は初めにあり、ありとして、二段でなし、なしと来る。そして三段目であり、ありである。三観で割り振るならば、なし(空)、あり(仮)、なし(中)となる。
この収まりの悪さは、ともすると既成概念に縛られ、悟りに迷う衆生の典型ではなかろうか、との思考が頭をかすめる。
一々の全てを「現成公案」とするならば、恣意的概念や思考形態を用いながら解釈する、その方法自体が、「現成公案」にて戒められるべきところ、なのではないかとも思う。
ここで、あらためて三段に対して、辛うじて理解に及びそうな仏教的文言を探り『般若心経』の下記三つの偈文を並べてみた。
空不異色(あり)
色即是空(なし)
空即是色(あり)
更に実際に『般若心経』中、「空」の含まれる偈文部分を、次第順に記してみたがその結果、あくまで『般若心経』との比較ではあるが、実に奇妙な組み方となっている。
「五蘊皆空」
「色不異空」
「空不異色」(あり)
「色即是空」(なし)
「空即是色」(あり)
「諸法空相」
「是故空中」
ここに至って「現成公案」の内容や『啓迪』の解釈に臨もうとするならば、教相的な素地も必要としながら、その決まった次第や概念にまで踏み込んで理解しようとすると、敢えて整合性が取れなくなる仕掛けでも施されているようにも見える。
私自身がまず、解釈すべき方法論でつまずき、更に内容中では教相的に一定に解釈されてきた概念で迷い、さらに解釈される順次次第でも悩まされた感がある。
『啓迪』を繰り返し読んでみると、一見すると同義に見える文言を、その前後全体の文章の通じる型に落とし込むべく、たくみに狭義と広義の解釈を判別して使用されていることが理解出来る。
なるほど、気付いてみれば皆これ自縄自縛であったのか、とも思えるのである。
あるいは「現成公案」に第二の意味があるとするならば、「跳出自縛」かもしれない。
西有禅師の『啓迪』はこのあたりを「これがどうも腹に入りかねる、それはなぜかというと、平常腹にあるものが道と違っているからだ。それをまず掃除して空っぽになって聞かないといかぬ。」と示される。
講座(5)『正法眼蔵』「現成公案」の巻の考察④
仏の教え