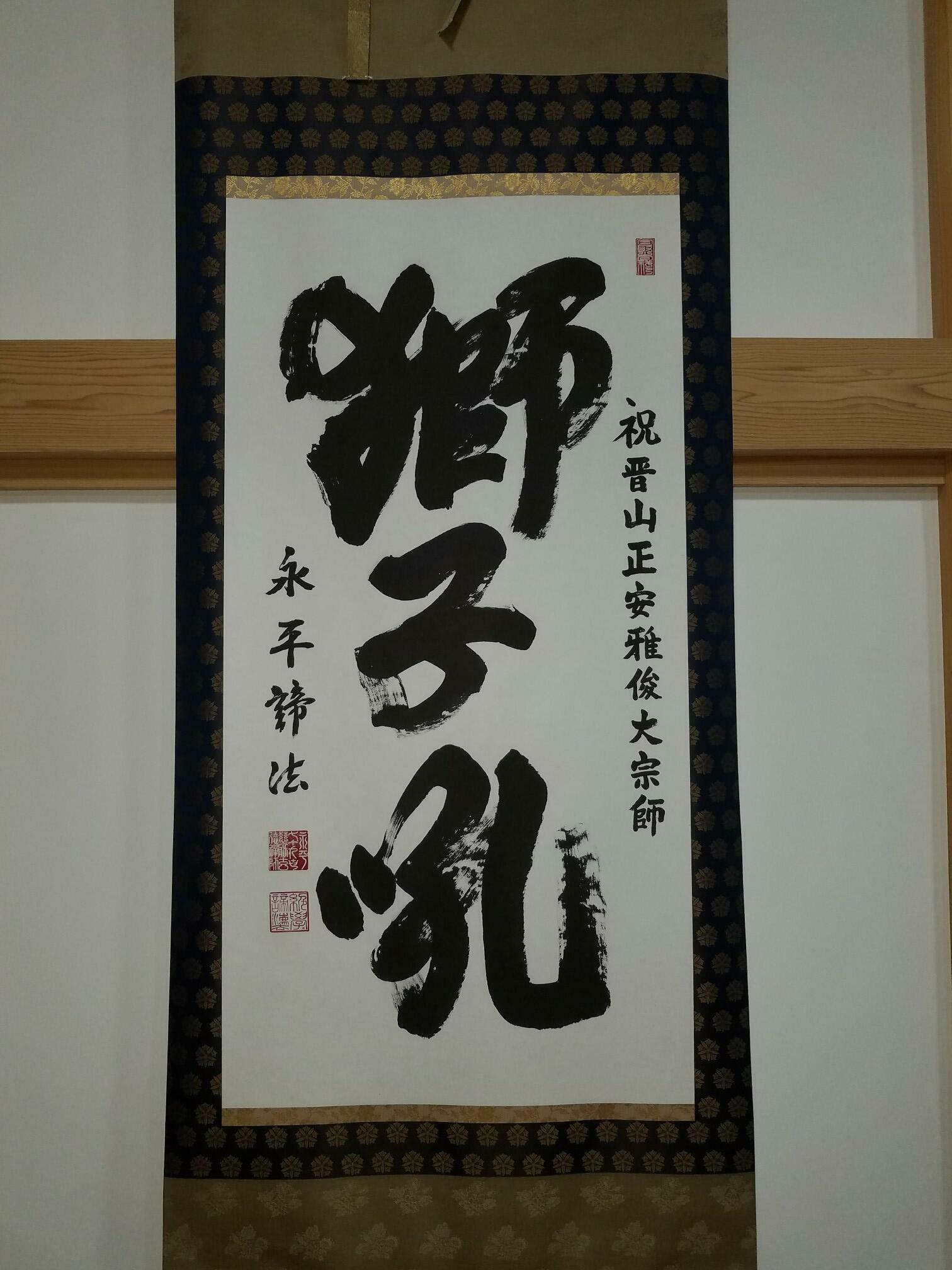第四段
本文
自己をはこびて萬法を修證するを迷とす、萬法すすみて自己を修證するはさとりなり。
語注
・自己...これも先述の『われ』と同様であるか。「諸法無我」の「我」であろうか。重要なところのようだが、どう訳したらよいか。そのまま「自分」でよいものか。
・修証...ここも重要そうであるが、難しい。通常「修行と悟り」という意だと思われるが、道元禅においては、「修証一等」の言葉があり、その修証と思われるが、私はまだ理解不足で分からない。
現代語訳〈緑本〉
自己の外に万法があると思って、自己から万法を修行し、実証しようとするのを迷いとし、万法の方から、自己の生きている真実を修行させられ、実証させられるのが悟りである。
自主的解釈
単純に訳するならば右記の通りだが、どうであろうか。前三段を解釈してきた後では、右の解釈は単調にも見える。とくに「はこびて」や「すすみて」の微妙なニュアンスが、しっくりこない。
『一定ではない「われ」から世界を見るのではない、世界の一部、世界そのものである自分の視点から見るのだ』というように訳したいのだが、そのための言葉を更に探求しなければならない。
『正法眼蔵』の解釈には単に学力や知識、修行経験や仏教学のみならず、相当以上の語彙力が必要であることが、今更ながらに理解出来る。
自己をはこぶ、移動し動かす、何処へ、修行に適した場所へ、修行に適した場所とは、と進め考えると、自己にしろ、万物の我にしろ、そこにその状態である意義を尊重する「現成公案」から見るならば、自を離れて他につく、または他を離れて自につく、現世を厭い浄土に就く、苦を厭い楽に就くを示すは、仏教を学ぶ初期段階、次第順序に重きを置く中では狭義の教えたり得るも、有無断常の両辺を離しながらまた、初後皆是とする本門的な見知からは、未だに心ここに在らずにして、彼に執している状態、いわゆる迷とするのであろう。
萬法すすみてというを、前句の対語と見るならば、万物の方から自己に證入せしむともいえる。そして、万物の證入なればこそ自己の我見ではない。無我の内であるから、さとりなりとも言えよう。
『啓迪』では、この辺りは難所であるとして、「まず大体をここの御文通り親しく解しておいて、それから後で何とでも称すべきである。」として、この時点における解釈としては、この判断をも可としている。
ただし私自身が、この解釈では薄もやに取り残された感がして、どうにも進みにくい。
対語としてではなく、単純端的に解釈するならば、万物に共通して進むのは時間である。時間的に事象をとどめ続けることがない事実を仏教では「諸行無常」と記す。
この解釈ならば仏法の根幹でもあり、諸行無常の法界の中にあって、自らそこを離れず、そのままの山河大地に在って行ずるならば、さとりなりとの解釈も理解し易い。
さてこの解釈ならばと思いはじめると、『啓迪』から待ったがかかる。
西有禅師が読み解くに、「現成公案」の一文句のみにあれもこれもと含めてしまえば、悪平等になりかねない。そこで「現成公案」と雖も迷いや悟りもあるという意を示すため、この段が用意されているのだとする。
しかも難所であるが故に、順次に工夫を重ねて進むべきところなれども、骨を折って記された古人の注釈である『参本』や『私記』も、学人には時期尚早たる内容で、かえって迷いかねないとして、一時そのまま御文通りに解し、四段の真意にはここより近づくのだという。
ここまで至って、さらに『啓迪』は御文を再解釈するのである。同じ御文「自己をはこびて萬法を修證するを迷とす」であっても、「はこびて」が残留するを迷とし、自己が自己を尽くし萬法と一様になった自他一如、迷悟一等の上での迷であるならば、諸法仏法中の迷悟であるから、この御文の迷も、単なる狭義の迷ではなく、證上の迷となり御文全体も広義的に悟と訳すべき解釈を示している。
常日頃から分別智を逞しくして生活している私達には、無分別智からの「悟」と「迷」と突然いわれても、よくわからない。
『大智度論』の「文殊師利本縁」において、「勝意菩薩の弟子たちは善と悪とを区別して、そのたびに心が動転したが、喜根菩薩の弟子たちは諸法は清浄であり罣礙する処無しの道理を知って、心穏やかだった...。」という所であろうか。
第五段
本文
迷を大悟するは諸佛なり、悟に大迷なるは衆生なり。さらに悟上に得悟する漢あり、迷中又迷の漢あり。
語注
・大悟...さとること。すべての迷いを打ち破り、絶対の真理と不二になること。
・得悟...さとりを得ること。
・漢......①おのこ。男子。原意は晋の五胡が中原を侵した時、漢の男子をののしった語に由来する。漢児。
②人のこと。禅の語録でいう。
③天の川。
現代語訳〈緑本〉
(こういう)迷いを大悟するのが諸仏であり、悟りを追い求めて大いに迷っているのが衆生である。さらに、悟りの上に悟りを得る漢(ひと)もいるし、迷いの中でさらに迷っている漢(ひと)もいる。
本文の出典元
・迷を大悟するは諸仏なり
:諸仁者、迷は則ち悟に迷ひ、悟は則ち迷を悟る。迷時力士は額上之珠を失ひ、悟は則ち貧子衣中之宝を獲る。(『会要』二十八、天衣義懐章)
自主的解釈
素直に解釈すれば「迷を大悟」するが諸仏であるから、こちらがさとりとなる。反して「悟に大迷」なるは衆生なりは、迷いとなる。
また「悟上の得悟」や「迷中又迷」するもあるという。
ここのところは仏教学概論として、随分親しく指導されたところでもある。曹洞宗門の禅または、修行とさとりの関係性については「修證一等」あるいは「修證不二」と述べられる。
であるならば修行を離して證はないので、悟ったというところで、修行が止んだら、證も失うこととなる。故に證は修の上でしか成り立たない。つまり悟上の得悟、宗門でいうところの「證上の修」となる。
また平生分別の世界で過ごす私達は、迷いの現世を離れて仏の世界、さとりを目指すべきを目的とする。
しかし前段にて述べられた如く「現成公案」、または諸法仏法とするならば、修證一等でありまた迷悟一等でもある。そこでは、悟りが有るかぎり迷いも有るという世界観が残される。
迷いが深くなれば、悟りの輪郭も愈々強くなり、益々迷いも勢いを増して消えにくくなる、という悪循環もここで示される。
よくよく考えるならば、文字言説を用いれば皆分別となる。分別によって対となる道理や現象を素早く理解出来る。
つまり半分を学べば、残りの半分は反対の意味であると示せば、知識や記憶の短縮にもなる。であるからこそ悟る時には必ず迷いが存在し、迷う時にも同時に悟りが存在し得る。
さてこの事実を知った上でこの御文を解説する場合には、全体をどう評するべきであろうか。互いが無ければ命名もされず、存在しえない本質、その上での迷悟である。
よって迷を悟るは、迷いと悟りが相対している迷中の悟り、すなわち狭義の悟り、あえて迷を「大悟」するというは、迷悟相対を跳出するを示した上での廣義のさとりとも解釈は出来まいか。
同様に「悟に大迷」なるを廣義にて解釈するならば、迷悟一如の道理の上で、その相対を跳出した迷でれば、迷いの迷ではなく諸法仏法上の迷とも訳せよう。
なれば「悟上得悟」も「迷中又迷」も上記、「悟に大迷」または「迷を大悟」の時節を変じた重複説明とも解釈出来る。
道元禅師は「生も一時の位、死も一時の位なり」の文言同様、同義なるものの時位を変じ記し、総じて迷悟断常を跳出した法界そのものを、現出せしめようとしたのではあるまいか。
このような解釈を可能としたのは、まさに前段までの複雑怪奇にも思えた解釈の経験があればこそである。
それまで僅かな時間さえ惜しみ与えぬ筆勢を、ここでは一旦落ち着かせ、端的な内容ながらも、じっくりと考える余地を与えられたようにも思える。
さて西有禅師はここで、悟上得悟を「悟迹を忘ずる」こと、迷に大悟するを「入処」とし、更に悟迹を忘ずるためにこそ、四十二の位階を必要と説かれる。
中国における大乗仏教発展過程では、四十位、四十二位、五十二位の違いは出典経典や歴史的経緯とも考えられる程の差異であるから、華厳に近い四十二位だとか、何故天台の五十二位を『啓迪』は用いない等の些末な論は控える。
ただしここでは、西有禅師も道元禅師同様の修證観、すなわち證上の修なればこそ、また初心・後心の階位や自身が修行の目安となるべき、位階次第も必要との見知であったと思われることのみを記す。
講座(5)『正法眼蔵』「現成公案」の巻の考察⑤
仏の教え